
Price: я┐е3,278
(as of Dec 25, 2020 00:59:16 UTC – Details)
хЗ║чЙИчд╛уВИуВК


ч╕ДцЦЗцЩВф╗гуБЛуВЙцШнхТМхИЭцЬЯуБоцЬНщг╛хП▓уБМф╕АчЫоуБзуВПуБЛуВЛя╝Б
уГ╗
щвиф┐ЧхНЪчЙйщдицЙАшФ╡уБочнЙш║лхдзф║мф║║х╜вуБлф╕АуБдф╕АуБдчЭАшгЕуБХуБЫцТох╜▒уБЧуБЯхЫ│чЙИуБиуБиуВВуБлуАБцЬНщг╛уБоцн┤хП▓уВТчФЯц┤╗цЦЗхМЦуБошж│чВ╣уБЛуВЙцЩВф╗гхИеуАБчФ╖хе│хИеуБлуБЯуБйуВЛф╕АхЖКуАВ
цШнхТМ57х╣┤уБохИЭчЙИуБЛуВЙц░╕х╣┤уБлуВПуБЯуБгуБжцдЬшиОуВТщЗНуБнуАБуВИуВКхЕЕхоЯуБЧуБЯхдзхвЧшгЬцФ╣шиВцЬмуБиуБЧуБжхоМцИРуБЧуБЯуАБф║ХчнТщЫЕщвиуАОхОЯшЙ▓цЧецЬмцЬНщг╛хП▓уГ╗хвЧшгЬхдзцФ╣шиВчЙИуАП(х╣│цИРхЕГх╣┤уАБхЕЙчР│чд╛хЗ║чЙИ)уБоф╕нуБЛуВЙуАБхе│цАзуБлщЦвуБЩуВЛщаЕчЫоуВТцКЬч▓ЛуБЧуАБч╖ищЫЖуБЧуБЯуВВуБоуБзуБВуВЛуАВ


чнЙш║лхдзф║║х╜вуВТчФиуБДуБЯхЫ│чЙИ
уГ╗
ф║║х╜вшг╜ф╜ЬуБохОЯхЫ│уВДцМЗх░ОуБпф╕╗уБлщвиф┐ЧхНЪчЙйщдич╛ОшбУходщХ╖уБМцЛЕх╜УуБЧуАБуБкуВЛуБ╣уБПуГкуВвуГлуБЩуБОуБкуБДф║мф║║х╜вуВТчФиуБДуБжуБЭуБоцЩВф╗гуБохз┐уВТчд║уБЩуБЯуВБуБлчЙ╣хИеуБкхо╣ш▓МуБМцдЬшиОуБХуВМуБжуБДуВЛуАВ
чФЯц┤╗цЦЗхМЦуБлуВИуВЛцЬНщг╛уБочЙ╣чХ░цАзуВТцЩВф╗гхИеуБлуБФч┤╣ф╗ЛуАВ






х╝ечФЯцЩВф╗гуААхе│чОЛхНСх╝ехС╝(хПдф╗гх╖лхе│)
уГ╗
хПдф║ЛшиШуВДцЧецЬмцЫ╕ч┤АуВИуВКуВВхПдуБДцЦЗчМоуБиуБЧуБжуАБцЧецЬмуБлуБдуБДуБжшиШуБХуВМуБжуБДуВЛуВВуБоуБМуАБф┐ЧуБлуБДуБЖщнПх┐ЧхАнф║║ф╝ЭуБзуАБуБУуВМуБпф╕ЙхЫ╜х┐ЧуБоф╕АуБдуБзуБВуВЛуАМщнПцЫ╕уАНуБоцЭ▒хд╖ф╝ЭхАнф║║уБоцЭбуБзуАБцЩЛуБощЩ│хп┐уБМф╕Йф╕Цч┤АуБлшСЧуВПуБЧуБЯуВВуБоуБзуБВуВЛуАВ
уГ╗
хоЙхЬЯцбГх▒▒цЩВф╗гуААцЙУцОЫуВТуБдуБСуБЯцнжхо╢ф╕Кц╡Бхйжф║║
уГ╗
цнжф║║уБохж╗уБкуБйуБпуАБшбгцЬНчЬБчХеуБощвиц╜оуБлф╝┤уБгуБжуАБх░ПшвЦуБоф╕КуБлч┤░уБДх╕пуВТч╡РуБ│хЮВуВМуАБш║лхИЖуБощлШуБДхйжф║║уБзуВВуАБф╕КуБлцЙУцОЫуБиуБДуБЖх░ПшвЦхРМх╜вуБошбгуВТф╕КуБЛуВЙх╝ХуБНуБЛуБСуВЛуБоуБ┐уБиуБкуВКуАБщлкуБпхЮВщлкуБлуАМуБ│уВУуБЭуБОуАНуБощлкуВТф╕бхБ┤уБлуБЯуВМуАБхМЦч▓зц│ХуВВуАБф╜ЬуВКчЬЙуВТф╕КуБоцЦ╣уБлцППуБПуВИуБЖуБлуБкуБгуБЯуАВ
уГ╗
цШОц▓╗уГ╗хдзцнгцЩВф╗гуААхе│хнжчФЯхз┐
уГ╗
хйжф║║уБМшв┤уВТуБпуБПуБУуБиуБпхоох╗╖уБлцЦ╝уБДуБжх╣│хоЙцЬЭф╗ецЭешбМуВПуВМуБжуБДуВЛуБУуБиуБзуБВуБгуБЯуБМуАБцШОц▓╗уБлуБкуБгуБжшв┤уВТчЭАчФиуБЩуВЛф╕АшИмхйжф║║уВВуБВуВЙуВПуВМуБЯуАВ
хдзцнгуАБцШОц▓╗уБлуБкуБгуБжуВВуАБхе│хнжчФЯуБпуБНуВВуБоуБоцЩВуБпч┤луБошв┤уВТуБдуБСуВЛцЕгф╛ЛуБМхПЧуБСч╢ЩуБМуВМуБжуБДуВЛуАВф╕ЛуБТщлкуБлуГкуГЬуГ│уАБчЯвч╡гуБох░ПшвЦуБлщЭ┤уВТуБпуБДуБжуБДуВЛуАВ
уГ╗
щооцШОуБкцМ┐ч╡╡уБишй│ч┤░уБкцЦЗхнЧшзгшкмуБзхИЖуБЛуВКуВДуБЩуБДя╝Б






цзШуАЕуБкуВвуГ│уВ░уГлуБЛуВЙцТох╜▒
уГ╗
уВИуВКщА▓х▒ХуБЧуБЯуВлуГйуГ╝цКАшбУуБлуВИуВКуАБф╕Ацо╡уБищооцШОуБкхЫ│чЙИуБМхоЯчП╛уБЧуБЯуАВхЕиш║луБпуВВуБбуВНуВУуАБшГМщЭвуВДцЙЛхЕГуАБх╕пуАБшг╛уБкуБйуБош│ЗцЦЩуВВхЕЕхоЯуБЧуБжуБДуВЛуБЯуВБуАБуБУуБоф╕АхЖКуБзщЪЕуАЕуБ╛уБзхоЯшжЛуБЩуВЛуБУуБиуБМуБзуБНуВЛуАВ
уГ╗
чЭАчЙйф╗ехдЦуБохРДчиош│ЗцЦЩуВВхЕЕхоЯ
уГ╗
цЩВф╗гуБош▒бх╛┤чЪДуБкцЬНщг╛уБлхКауБИуБжщлкуБоч╡РуБДцЦ╣уВДшгЕщг╛хУБуБлуБдуБДуБжуВВшзжуВМуВЙуВМуБжуБКуВКуАБуБУуБУуБзуБпц▒ЯцИ╕цЬлцЬЯуБЛуВЙцШОц▓╗уБлуБЛуБСуБжуБохДкуВМуБЯхйжф║║чФиуБошвЛуВВуБоуБМч┤╣ф╗ЛуБХуВМуБжуБДуВЛуАВ
уГ╗
х╖╗цЬлуБлуБпчФишкЮшзгшкмуВВ
уГ╗
цзШуАЕуБкшгЕщг╛хУБуБохРНчз░уВДх░ВщЦАчФишкЮуВВхдЪуБПчФиуБДуВЙуВМуБжуБДуВЛуБМуАБчФишкЮшзгшкмцмДуБлуБжф║ФхНБщЯ│щаЖуБзуБЩуБРуБлцДПхС│уВТшк┐уБ╣уВЛуБУуБиуБМуБзуБНуВЛуБЯуВБуАБуБУуБоф╕АхЖКуБауБСуБзцЧецЬмцЬНщг╛хП▓уБохдЙщБ╖уВТф╜УщиУуБзуБНуВЛуАВ
уГ╗
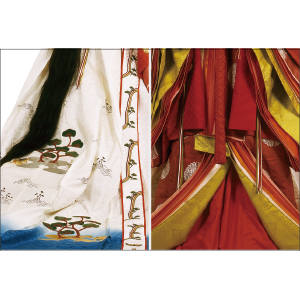
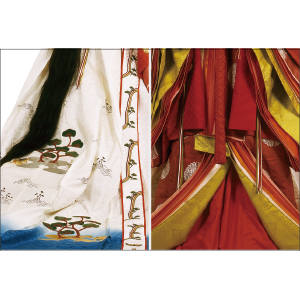
цЬНщг╛хП▓чаФчй╢уБох┐ЕчД╢цАзуВТцФ╣уВБуБжшжЛуБдуВБуБЯуБД
уГ╗
ф║║щЦУуБМчФЯц┤╗уБЩуВЛуБЖуБИуБзцЬАуВВхдзхИЗуБкф╕ЙшжБч┤атАЭшбгщгЯф╜ПтАЭуБоф╕нуБзуАБхЛХуБПф║║щЦУуБих╕╕уБлуБиуВВуБлуБВуВЛуВВуБоуБпшбгуБзуБВуВКуАБцЬНщг╛уБиуБпцЬАуВВх╖▒уВТшбичП╛уБЧуБЖуВЛцЙЛцо╡уБзуБВуВЛуАВ
цЬНщг╛уВТщАЪуБШуБжуБ┐уВЛхз┐уБМф║║щЦУуБоцЦЗхМЦуБзуБВуВКуАБф║║щЦУуБочФЯц┤╗уБЭуБоуВВуБоуБзуБВуВЛуБиуБДуБгуБжуВВщБОшиАуБзуБпуБкуБДуАВ
чеЦхЕИуБох┐ГуВТчЯеуВКуАБчФЯуБНуБжуБНуБЯхз┐уВТчЯеуВЛуБУуБиуБМшЗкх╖▒уБохз┐уВТчЯеуВЛуБУуБиуБзуБВуВКуАБцЦЗхМЦуВТщА▓уВБуАБшЗкуВЙуБочФЯуВТхЕиуБЖуБЩуВЛцЙАф╗еуБзуБпуБкуБДуБЛуАВ





уГмуГУуГеуГ╝
уГмуГУуГеуГ╝уБпуБ╛уБауБВуВКуБ╛уБЫуВУуАВ